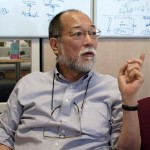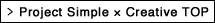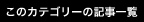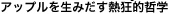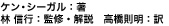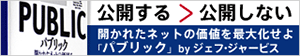- HOME Simple x Japan
- Simple x Japan 妹尾堅一郎氏インタビュー 前編
世界を変えるひらめきは、いつもシンプルだ。
妹尾 堅一郎氏(特定非営利活動法人 産学連携推進機構 理事長、CIEC会長)
1953年東京都生まれ。特定非営利活動法人 産学連携推進機構 理事長、CIEC(コンピュータ利用教育学会)会長。慶應義塾大学経済学部卒業後、富士写真フイルム(現富士フイルム)に入社。1990年、英国立ランカスター大学経営大学院システム・情報経営学博士課程満期退学。産能大学助教授、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授、東京大学先端科学技術研究センター特任教授などを経て現職。一橋大学大学院MBA、九州大学、放送大学の客員教授を兼任。内閣知的財産戦略本部専門調査会会長、経済産業省産業構造審議会競争力委員会委員、農林水産省技術会議委員など、多数の政府委員を務める。著書に、『技術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるのか』(ダイヤモンド社)、『アキバをプロデュース』(アスキー新書)など多数。
[妹尾堅一郎氏インタビュー]
| 2012.06.16 | Simple x Japan 妹尾堅一郎氏 インタビュー 前編 |
|---|---|
| 2012.06.21 | Simple x Japan 妹尾堅一郎氏 インタビュー 後編 |
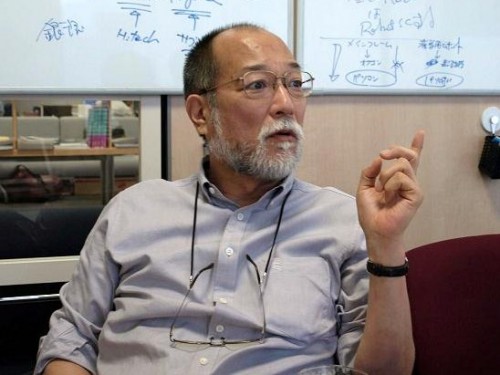
- “Think Simple”という言葉から、妹尾さんは何を想起しますか?
- イノベータが共通して持つ感覚が見事に表現されていると見えます。それまでの世の中で当たり前と思われていた世界観、あるいはモデルを覆す概念は、実はそう複雑なものではありません。単純明快な、しかし斬新な言葉やコンセプトなのです。スティーブ・ジョブズは世界の、特に日本のエレクトロニクス産業が「技術力があれば、事業でも勝てる」という思い込みで身動きでなくなっていたときに、「面白さが世界を変える」というシンプルな発想、つまり“Think Simple”で競争をまったく別の次元、しかも自分たちが得意な場所に移行させてしまったわけです。そして、その競争の根底にあった考え方こそ、印象的なキャッチコピーである“Think different”(違ったことを考えようぜ!)だったといえます。
“イノベーション思考”は二軸で成り立っているといえるかもしれません。ひとつはThink Simple 対 Think complicated、もうひとつはThink different 対 Think the sameの軸です。この2×2のマトリクスの中で、ジョブズはこのThink SimpleとThink differentの象限を生き抜いてみせたといえますね。だから、強かったんです。そして、これはすべてのイノベータに共通しています。例えば、ソニーの創始者である盛田昭夫氏もそうだった。ウォークマンだって、技術があったから創ったのではなくて、盛田さんが面白いと思ったからやったわけです。つまり、商品企画というデザインが先にあって、それを体現するために技術が開発されたのです。常にワクワクしたことをやろうという発想。これが日本初、世界初を生み出し、文字通り日本を変え、世界を変えていったのです。ホンダをつくった本田宗一郎さんも同じでした。
- 今ソニーの例が出ましたが、日本のイノベータにこれから求められることは何でしょうか?
- まずは技術を極めれば事業競争に勝てるという幻想を捨てることですね。この発想で勝てる時代は1980年代で終わっているんです。欧米企業は自分たちの技術力をどう活かせば事業競争力になるのか、その工夫を凝らし始めた。あるいは、どういった次世代の産業生態系を仕掛ければ、自分達の事業が優位になれるかを考え抜いてきている。一番重要になる前提は、どうすれば社会や顧客に新しい価値、ワクワクする価値を提供できるかということです。そのコンセプトやイメージを発想できるビジネスリーダーやリーディングカンパニーがこの30年間にたくさん生まれてきた。一方で日本にはそうした例が数えるほどしかない。
例えば、最近の電機メーカーの惨敗の原因の一つであるテレビ事業。従来の延長線上で多機能化すれば勝てるという幻影を捨てきれなかった。テレビをテレビ番組の受像機として使う時代なんてとっくに終わっている。「テレビ番組をテレビ放送サービスを通じてテレビ受像器で見る」と言う意味での「テレビを見る」という言葉は、もう死語になったのです。身の回りを見れば歴然としていますよね。若い人は、テレビも映画もインターネットの動画サイトも、テレビのみならず、パソコンでもスマートフォンでも見ているのです。にもかかわらず、未だにやれ3Dだ、高解像度だ、多チャンネル同時録画だ、という発想でテレビを開発して売っているわけです。だから、秋葉原の電気街の店主たちが日本のメーカーに怒っているのは当然です。機能を複雑多様化するのは改良であってイノベーションではないのです。
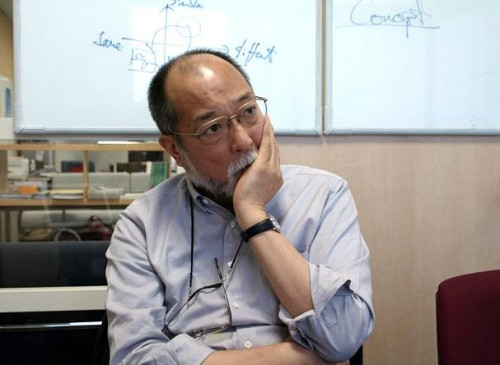
- 欧米企業におけるイノベーションの考え方に代表されるものとは何でしょうか?
- 私がよく話すのは、インテルのインサイドモデルです。「インテル入ってる」のコピーでおなじみのインテルはかつてメモリー(DRAM)を開発した企業でした。しかし、それに追随した日本の企業群に徹底的に負けました。つまり、「技術で勝って、事業で負けた」のです。そこで、アンディ・グローブ(インテルの当時のCEO)は自分たちの技術を活かして勝てる事業モデルをどう生み出すか、それを徹底的に考え抜いた。そして、パソコンの基幹部品であるMPUのすぐれた急所技術に特化して研究開発を行い、ブラックボックス化しました。その上で、周辺部品をつなげるためのインターフェースプロトコルだけを国際標準としてオープン化する手法を思いついたのです。
これによって、自分たちの特化した技術という知的財産(知財)は守られ、他社メーカーはオープン化された標準規格に則って関連部品を自由に開発するようになる。今で言う「プラットフォーム」を主導的に形成したわけです。それが成り立てば、パソコンが作られれば作られるほど、自分たちの技術が使われると同時に、パソコンが売れれば売れるほど、自分たちのMPUが売れるわけです。これをビジネスモデルと言わずして何と言うのでしょうか。これが、単なる技術競争を超えて、技術を活かして事業で勝ち続けるようにしたインテルのイノベーションでした。つまり、技術のイノベーションではなく、ビジネスモデルのイノベーションです。これが発展して現在、多くの勝ち組企業が採用する「オープン&クローズ戦略」(自社技術をクローズにする一方、普及に寄与してくれる部分をあえてオープンにして他社に提供するという組み合わせを行う戦略)になったのです
- イノベーティブな事業を起こすためにはどんな視点が必要でしょうか?
- 次世代のワクワクするような価値を想像し、それに即した産業生態系を想像する力ですね。そして、そのどこで自分の事業が勝てるかを設計できる力です。言い換えれば、「商品形態(次世代の産業生態系において、どのような製品やサービスのどこを自分達が扱うべきか)」と「事業業態(その商品を通じてどのような価値をどのように提供し、その対価としてどのような価値を顧客から得るビジネスモデルにするのか)」を想像できることです。もちろん、ここで想像するにあたって重要なのはThink differentですね。すなわち、他の人の考えないイメージを形成できるかどうかです。想像=創造なのです。そのためには、現世代の商品形態や事業業態の構造を見抜く力がなければなりません。単に勉強するためではない。それらを学ぶのは、現世代のものを超えるためです。
ここで、先程のインテルのインサイドモデルに加えてアップルのアウトサイドモデルをお話しましょう。アップルがiPod、iPhoneを出したとき、最初はみんなこう言いました。「中身は全部日本製」「ほとんどすべて、既存の技術で作られている」と。ではなぜ、日本はiPod、iPhoneを生み出しえなかったか。それは、アップルのビジネスモデルの恐ろしさを見抜くことができなかったからです。インテルの時もそうでした。日本の多くの企業人は技術に目が行って、ビジネスモデル(商品形態や事業業態)を解析できないんです。その訓練さえやっていない。教科書さえ十分に揃っていない。アップルは、まず価値形成を想像して事業全体をデザインした。すなわち、アウトサイドをしっかりさせた。その上で、自分たちの技術力をどこに集中し、どこを他人に任せればよいのか、その全体のデザインを想像=創造できたのです。だからこそ、自分たちの得意分野であるサービスの創造(iTunes Store)と、インターフェースの技術には徹底的に力を注ぎ、それ以外に必要な技術部品は全て外部から調達したのです。自分たちの得意分野に特化して、外部を従属させたわけです。「中身は全部日本製」とえばっても、その多くは「下請けに使ってもらっている」に過ぎないのです。この現実を直視すべきでしょう。
これらのモデルは、いってみれば非常にシンプルな発想です。要は内側(インサイド)から攻めるか、外側(アウトサイド)から攻めるかの違いがあるだけです。重要なのは、自分たちの知をいかに活かすか、そのコンセプトを考える力なのです。ただし、これは “知を活かす知”の思考感覚を持つリーダーがいないと、まったく読み解けない。そして、この構造を読み解けない企業は、すべて負けていく。今、イノベーションの世界では、こうしたパラダイムシフトが起こっているのです。